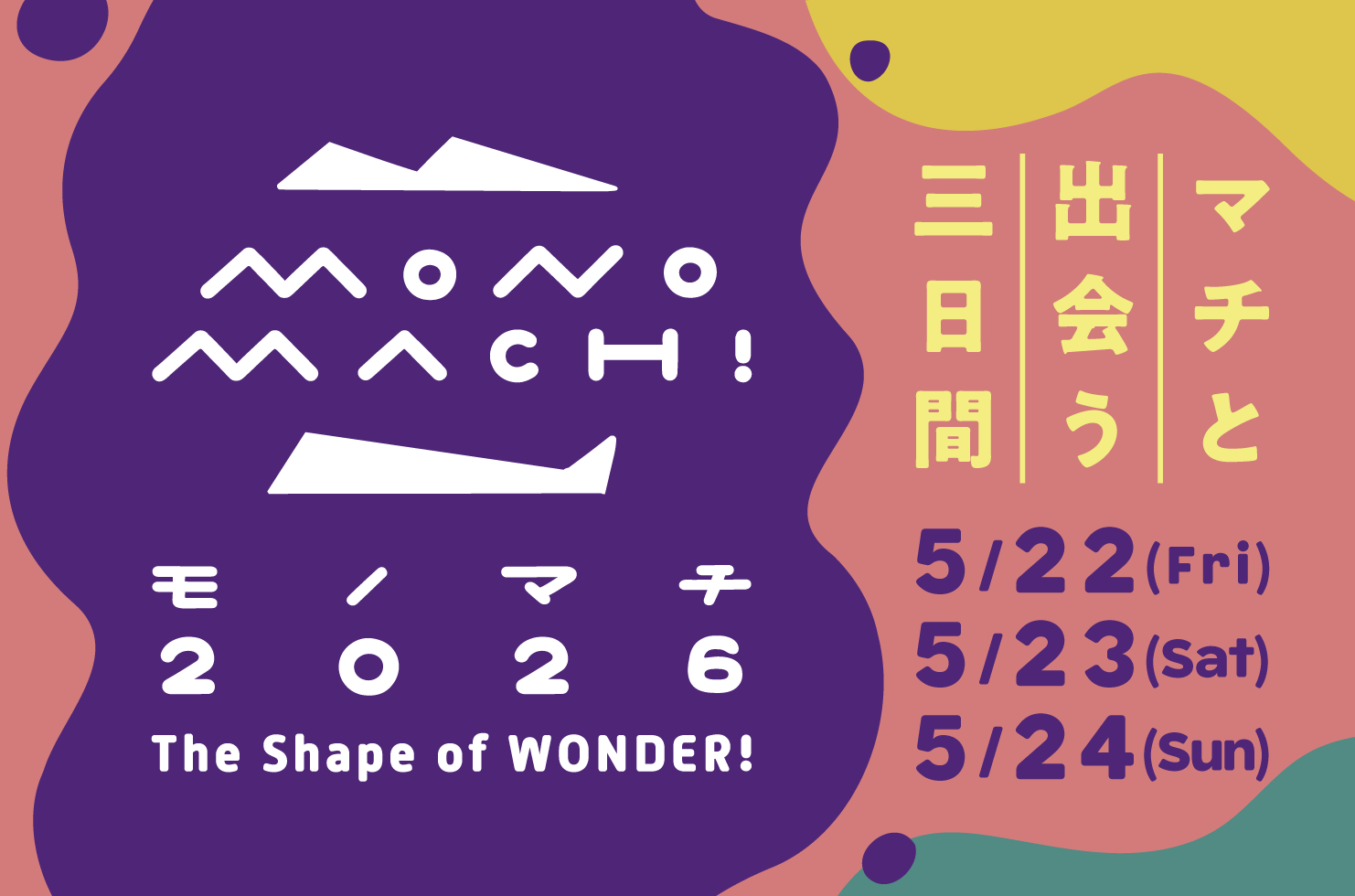ジュエリーに再び命を吹き込む“修理”という仕事

Woody Bell/atelier Woody Bell
鈴木広宣さん
業界でも一目を置かれる確かな技術
「お気に入りだったジュエリーが流行遅れになってしまった」「大切なリングのサイズが合わなくなってしまった」などの理由で、大事にしていたジュエリーを家の中で眠らせたままにしていませんか? そんな方にぜひ注目していただきたいのが、東上野にあるジュエリー工房「Woody Bell」です。
「Woody Bellは、ジュエリーのサイズ直し等の修理をメインに請け負っている工房で、なかでもハイジュエリーを中心に特殊な修理を得意としています。せっかく素敵なジュエリーを持っていても、流行の移り変わりや体型の変化などによって身につけられなくなると、そのままあきらめてしまう方が少なくありません。でも実は、リフォームや修理によって蘇る可能性は大いにあるんです。その方の大切なジュエリーに再び命を吹き込みたい──それがWoody Bellの願いです」と代表の鈴木広宣さんは語ります。
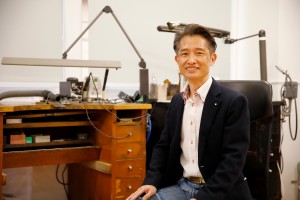
Woody Bell/atelier Woody Bell代表の鈴木広宣さん
たとえば、リングのサイズ直し。多少の調整であれば、購入したお店に頼めばやってもらえるのでは? そう思いますよね。でも、ただサイズを直せばよいという単純なものではなくて、サイズを変えることで見た目が変わってしまったり、ついていた石がはずれてしまったり、といったアクシデントが起こる可能性もあります。そのため、多くの百貨店やブランドでは、そうしたリスクを伴う修理は最初からお断りするというのが一般的なのだそうです。
そうした業界において、鈴木さんは30年以上にわたり、修理に特化して腕を磨いてきました。その確かな技術は口コミでじわじわと伝わり、かなり難易度の高い修理であっても、「御徒町のWoody Bellさんなら直せるらしい」と一目を置かれる存在となりました。有名ブランドからも絶大な信頼を得ているWoody Bellですが、そもそもなぜ、鈴木さんはジュエリー業界のなかでも“修理”という道を選んだのでしょう。そのきっかけを伺いました。
「高校時代、進路をどうしようか迷っていたとき、共通の趣味を通じてたまたま知り合った方が、指輪などをつくる職人だったんです。この業界は基本的に分業で、つくる職人、石留の職人、仕上げの職人、修理する職人と分かれているのですが、その方はつくることを本業にしつつ、修理も手掛け始めていました。そんなときに知り合って、ちょっと手伝ってくれないかといわれ、毎日のように工房へ遊びにいくようになったんです。そこで修理のしかたを教わったのですが、やってみるとこれがおもしろくて、そのまま親方の元で修業することになりました」(鈴木さん)
“修理”という仕事だからこそ感じられる喜び
こうして偶然の出会いから始まった、ジュエリー業界での第一歩。鈴木さんはコツコツと修業を重ね、1994年、22歳のときに独立し、Woody Bellを設立しました。当時、修理を専門で請け負う工房というのは非常に珍しく、業界ではかなり異色の存在として見られたとのこと。それでも、鈴木さんのなかには確固たる信念がありました。
「周りからは『修理で食べていけるの?』という目で見られましたが、でも、修理って絶対になくならないので。つくる仕事は工賃が安い海外へ流れてしまう可能性がありますが、直すとなると海外よりも日本の方がお客様は安心感があるので、修理の需要は絶対になくならないと思っています」(鈴木さん)

鈴木さん専用のデスク。修理ではさまざまな道具を使いますが、きれいに整理整頓されています
なるほど……。確かに、修理に出してでも手元に置いておきたいということは、それだけ大切なものであることの証。であれば、思い通りにきちんと直してくれる信頼できる職人さんに依頼したいと思うのは当然のことですね。

バフという研磨道具を回転させて指輪などを磨き上げるバフモーター

レーザーで金属を接合するレーザー溶接機。貸し工房「atelier Woody Bell」では、こちらの機械も使用することができます
「それと、つくる仕事というのはゼロの状態からつくるわけですが、修理というのはお客様がすでにお持ちのものを直すことが多いので、そのジェリーにはその方の思い出などが詰まっているんです。たとえば、お母さまやおばあさまの遺品として受け継いだジュエリーがあるけれど、サイズが合わない。でも、どうしても直して自分で身につけたい、というケースがよくあります。つい先日も、お母さまの遺品の指輪を持ってこられた方がいて、サイズを直したいけれど、いろいろなところで断られてしまった、と。確かにちょっと難しい修理だったのですが、どうにかうまく直すことができて、それを渡した瞬間、「お母さん……」といって、泣き出してしまったのです。同じようなことをこれまでに何度も経験していて、そのたびに“修理って最高だな”って思うんですよね。もちろんゼロからつくることの大切さ、難しさもありますが、修理というのは“心”が絡んでくるので、やっていて良かったなとしみじみ思います」(鈴木さん)
ただジュエリーを直すだけでなく、その方の大切な思い出の品を蘇らせ、未来へとつなげる──。そんな大切な役割りを担っているのですね。
後継者を育てるために、技術や知識は惜しみなく伝える
修理という分野において、業界で確固たる地位を築いてきた鈴木さんですが、2022年には「atelier Woody Bell」という彫金教室と貸し工房を開設しました。

「atelier Woody Bell」では、彫金用のデスクはもちろん、道具も豊富に取り揃えています
彫金教室は、道具の使い方などの基本が学べる「彫金ベーシックコース」、基礎を学んだあとに実際にアイテムを制作する「彫金総合コース」、銀粘土を使った彫金に特化した「銀粘土インストラクター習得コース」、そして、専門の職人から特定の技術が学べる「カスタムコース」があります。生徒さんは、すでにジュエリーの仕事をしている人からあくまでも趣味で楽しみたい人まで、実にさまざま。基本的にマンツーマンなので、個々の目的や実力に合わせて教えてもらうことができます。そして、「atelier Woody Bell」の最大の特徴は、鈴木さんがこれまでに培ってきた技術や知識を惜しみなく教えていること。これこそが、鈴木さんが一番やりたかったことだといいます。

生徒一人ひとりに合わせて、きめ細やかな指導をする鈴木さん。ちょっとした疑問にもわかりやすく答えてくれます
「今、どこも後継者不足に悩んでいますが、ジュエリー業界も同じです。職人の世界というのはとかく閉鎖的になりがちですが、もっとオープンにして後継者を育てていかないと、10年先には職人がいなくなってしまう。なので、少しでも生徒を増やして、そのなかから1人でもいいから職人になってくれたら、という気持ちです」(鈴木さん)
ひと昔前は「背中を見て仕事を覚えろ」というのが暗黙の了解でしたが、もはやそんなことを言っていられないほど、近年の後継者不足は深刻な問題。その危機感を感じ、後継者育成を決断されたのかと思いきや、鈴木さんからは意外な答えが返ってきました。
「いずれ人に教えるということは、この業界に入った当初から考えていました。親方のところで修業を始めてまだ1年も経っていないころ、業界新聞の取材でほかの職人さんと対談する機会があって、その記事で『今後、後継者を育てていきたい』と発言していたんです。自分はまったく覚えていなかったんですが、つい数年前にその新聞社の社長から『お前、こんなこと言ってたぞ。今、まさにそのとおりのことをしてるよな』といわれて、『あ、ほんとだ!』となりました」(鈴木さん)
まだ10代の青年が、しかも、業界に入って間もないときに「後継者を育てたい」と発言していたとは、なんともビックリです。鈴木さんって、予知能力でもあるのでしょうか……!?
「実は、どの職種についたとしても、自分が身につけた知識や技術を誰かに伝えたい、という気持ちはずっとありました。“広宣”という名前は、仏教の“広宣流布”という言葉からとったもので、広宣流布とは、法華経の教えを広く宣(の)べ伝えて広めることを意味します。これを自身に置き換えると、自分の知識や考え方を人々に広めていくということになり、そのような名前を授かったのであれば、この道でがんばっていこう、と。そういう運命を与えてくれた親にも感謝しています」(鈴木さん)
まさに、初志貫徹。確固たる信念をもち、真っすぐそこに向かって歩みを進め、そして今、こうして実現している。その一貫した生き方には、ただただ脱帽です。
職人が第2の人生でも活躍できる形をつくりたい
「人に教えるために、というのが根源にあって、そのために技術を勉強し、知識を身につけ、人脈を広げてきました。難しい修理を一生懸命がんばってやってきたのも、知名度を上げるため。なぜかといったら、自分が教えた生徒さんが、『あのWoody Bellさんで勉強してるなら、大丈夫だね』といわれるような教室にしたかったからです。だから、どうやったら人に伝えやすいか、ということをずっと勉強してきました。人に教えるというのはめちゃくちゃ難しくて、自分がわかっていることは相手もわかるだろう、と思ってしまいがちです。でも、それでは教えることはできない。あるとき、初めての方はどんなふうに感じるんだろう、とずっと考えて、よし、利き手とは逆の手でやってみよう、と思いついて試してみたんです。すると、利き手なら簡単にできることが、逆の手でやると全然できない。あ、これが初めての人の感覚だ!とわかって、どうやったらうまく伝えられるかというのが見えてきました」(鈴木さん)

教室では動画を使って解説することも
実際、教室に通う生徒さんからは「とってもわかりやすい」という声が多く聞かれ、目に見えて上達する方もたくさんいらっしゃるとのこと。これも「どうやったら伝えられるか」を追求し、きめ細やかな指導をしてきた鈴木さんの努力の賜物でしょう。
「カッコよくいうと、人生を捧げてきた感じですかね。この教室のために」と鈴木さん。まさに、これこそが鈴木さんのライフワークといえるでしょう。最後に、今後の展望を伺いました。
「これからも生徒を増やして教室を大きくしていきたいというのもありますが、生徒を育てるだけではなく、講師も育てていきたいですね。そして、ゆくゆくは現役の職人を講師として育てたいと考えています。自分も長年、職人業を続けてきたなかで、すごく腕のいい職人さんが引退されていく寸前の淋しさを目の当たりにしてきました。現役のころは仕事がバンバン入ってきたのに、歳とともに仕事も減っていって、暮らしぶりも一変してしまう。それはあまりにもやりきれないな、と。なので、まだ現役のうちに講師としての勉強をしてもらえれば、現役のイメージのまま講師になって、第2の人生でも活躍できる──そういう形をつくっていきたんです。そのためにも、生徒を増やすとともに講師陣も充実させて、今以上に『いい教室だね』といわれるようにがんばっていきたいと思います」(鈴木さん)
“人々に伝え、広める”という生涯のミッションを胸に、さらなるチャレンジを続ける鈴木さん。Woody Bellのますますの発展が楽しみです。
なお、Woody Bellは2025年5月のモノマチに初参加します! 銀粘土でオリジナルのイニシャルチャームをつくるワークショップを開催しますので、気になる方はぜひ、ホームページをチェックしてみてくださいね。

モノマチで開催予定のワークショップでは、写真のようなイニシャルチャームがつくれます
Woody Bell/atelier Woody Bell
東京都台東区東上野1-1-8 竹内ビル2F
TEL : 03-5688-2390
URL : https://woodybell-j.com/(Woody Bell)
https://woodybell-j.com/kb/ (Atelier Woody Bell)
PHOTO:HANAE MIURA
TEXT:MIKI MATSUI